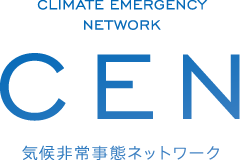子供の頃、「釣りキチ三平」という漫画がありました。その中で、釣りの天才少年の三平が四万十川で「アカメ」という幻の怪魚に挑戦する話がありました。たぶんそれがアカメという名前を初めて知った時だと思います。目が赤くて体が大きく、結構怖いイメージがあったのですが、これがまたすごい魚だったんだということを最近になって知りました。
去年9月に大阪医科薬科大学などが、アカメのゲノム解析の研究について発表しました。
ゲノム解析から探る「幻の怪魚」アカメの進化と生存の歴史(2024年9月24日 大阪医科薬科大学)
3万年ほど前から今まで、個体数たった1,000匹程度で生き延びてきたのです。信じられないほどタフです。絶滅が危惧されている魚ではあるのですが、「いやまあ、俺たち昔からこれでやって来てるんで、どうってことないっス」という声が聞こえてきそうです。
ゲノムを調べたら、種内の遺伝的多様性は低いのに、免疫に関わる遺伝子については高い多様性が保たれていることも分かりました。「フランス人は10着しか服を持たない」なんてことをどこかで聞いたことがありますが、アカメは余計なものは持たず、大事なものだけをしっかり持って厳しい自然界をタフに生き抜いて来た、ということなんですね。なんだかカッコいいですね。
さて、龍谷大学の主催で生物多様性についてのシンポジウムが開催されるのでご案内します。
名称:シンポジウム「ネイチャーポジティブへの挑戦 – 生物多様性の喪失は誰の問題で誰がどう解くのか」
日時: 2025年3月14日(金)13:00~17:00
会場: 龍谷大学(京都市)
主催: 龍谷大学 生物多様性科学研究センター
参加費: 無料
主な内容: 下記HPより抜粋
○開会あいさつ
深尾 昌峰(本学政策学部教授/副学長)
【第一部:生物多様性に関する調査や取り組みの報告】
・報告1 「ネイチャーポジティブをどう解くのか:難問の共有から小さな成功例の発信へ向けて」
山中 裕樹教授(本学先端理工学部/生物多様性科学研究センター長)
・報告2「地域のネイチャーポジティブ実現に、企業はどう貢献できるか」(仮題)
増澤 直氏(株式会社地域環境計画 生物多様性推進上席マネージャー/NPO法人地域自然情報ネットワーク 副理事長)
・報告3「人と人、人と自然をつなぐ市民コミュニティ財団の可能性」
山口 美知子氏(公益財団法人東近江三方よし基金 常務理事兼事務局長)
・報告4「ダイフクの環境の取り組み」(仮題)
三好 順子氏 (株式会社ダイフク サステナビリティ推進部 環境品質グループ)
・報告5「ネイチャーポジティブ×地方創生:自然と共に生きる地域づくり」
奥村 浩気氏 (滋賀県琵琶湖環境部 環境政策課企画・環境学習係)
・報告6「資料を未来に引き継ぐ博物館のこれまでとこれから」(仮題)
今田 舜介氏(滋賀県立琵琶湖博物館 学芸員)
【第二部:保全のための社会システムの構築に向けたパネルディスカッション】
・パネルディスカッション1
「生物多様性調査の価値とそのシステムの確立・維持について」(教育、研究、市民活動、啓発)
モデレーター:山中 裕樹教授(本学先端理工学部)
パネリスト:増澤 直氏(株式会社地域環境計画)、今田 舜介氏(滋賀県立琵琶湖博物館)、奥村 浩気氏 (滋賀県琵琶湖環境部)、岸本 直之教授(本学先端理工学部)
・パネルディスカッション2
「生物多様性データを基軸とした保全のための社会システムの構築に向けて」
(保全予算の内部化、行政施策、金融)
モデレーター:深尾昌峰教授(本学政策学部)
パネリスト:山口 美知子氏(東近江三方よし基金)、三好 順子氏(株式会社ダイフク)、山本 卓也氏(滋賀銀行 総合企画部)、只友 景士教授(本学政策学部)
○コメント 東洋紡株式会社
○閉会あいさつ 山中 裕樹教授(本学先端理工学部/生物多様性科学研究センター長)
詳しくはこちらをご覧ください。