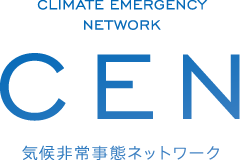「大気汚染なんかの話に出てくる”エアロゾル”って、よく殺虫剤スプレーのことを指して言う”エアゾール”となんか似てるよな・・・」と前から気になっていたのですが、確認してみたら、意味は同じなんだってことが分かりました。日本エアロゾル学会の説明によれば、「気体中に浮遊する微小な液体または固体の粒子と周囲の気体の混合体」をエアロゾル(aerosol)と言います。空気中を漂う粉塵、煙、霧、もや、スモッグ、花粉などですね。
このエアロゾルについて、今年1月30日に海洋研究開発機構と国立極地研究所がひとつの研究成果を発表しました。
シベリア森林火災が遠く離れた洋上の雲のもととなる?
ー高緯度洋上で測定した氷晶核濃度とエアロゾル成分濃度の比較からー(2025年1月30日、国立極地研究所)
シベリアの森林火災で発生したエアロゾル粒子が3,000~5,000kmもの距離を1週間くらい風に流されて西部北太平洋や北極海にまで飛んできていたことが分かりました。
エアロゾル粒子が「氷晶核」となって氷の結晶(氷晶)ができますが、雲の中の氷晶と水滴の割合は、太陽光の通過量や反射具合、雲のなくなりやすさ(降水過程)といった雲の性質を左右するそうです。
今回の調査では、これらの海域で東京都心に匹敵あるいはそれ以上の氷晶核濃度が観測されたそうです。これ、見渡す限り海しかないようなところですよね。そこに都心並みのエアロゾルがあるということなんですよね。いやもう、なんだかすごい話です。
シベリアなどの北方林で起こる火災から生じるエアロゾルが、数千キロも移動して北極海など高緯度の海洋上にやってきて氷晶核の供給において重要な役割を果たしている可能性がある。このことを初めて示した研究です。
これまでよく分かっていなかった要素が新たに加えられて、気候変動の分析や予測の精度がまた一つ上がることを期待しています。
さて、埼玉県環境化学国際センターの主催で「気候変動適応・生物多様性保全サイエンスカフェ」が開催されるのでご案内します。
名称: 気候変動適応・生物多様性保全サイエンスカフェ「気候変動対策としての森林保全に求められるもの」
日時: 2025年3月14日(金)15:00~16:30
会場: オンライン
主催: 埼玉県環境科学国際センター(埼玉県気候変動適応センター・埼玉県生物多様性センター)
参加費: 無料
主な内容: 下記HPより抜粋
世界的な森林現象や劣化により温室効果ガスが増加しています。特に熱帯地域で大きな問題となっていますが、なぜ熱帯林は減少・劣化しているのでしょうか。地域住民が生活の糧を得る場でもある熱帯林の特徴を踏まえ、先進国で生活する私たちにはどんな取り組みが出来るのかを考えます。
スピーカー:平塚 基志 氏(早稲田大学人間科学部)
ファシリテーター:長谷川 就一 (埼玉県環境科学国際センター 主任研究員)
詳しくはこちらをご覧ください。